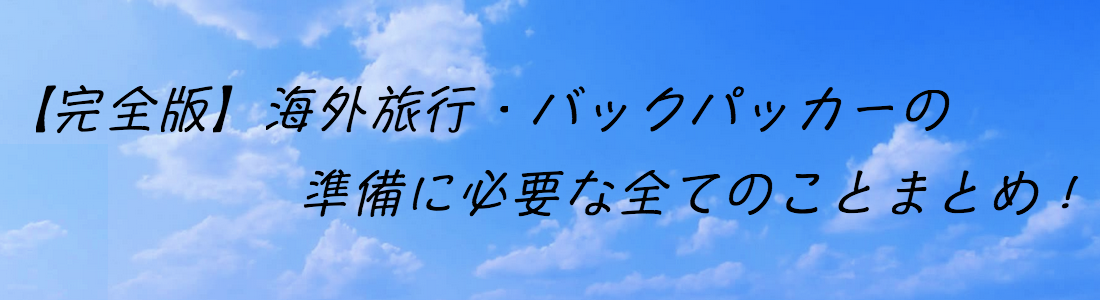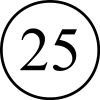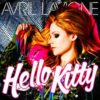【幽霊たち – ポール・オースター】何も物語が動かない孤独な物語
80年代アメリカ文学の代表的作品と謳われる本作。私は本書が大好きで既に何回か読んでいる。ポール・オースターの作品というとまず思い浮かぶのがムーンパレスではあるが、幽霊たちこそポール・オースターの魅力が凝縮された作品だと言いたい。彼の特徴を一言で表すと、何も物語が進展しない中で動く心情の表現、この点が他の作家に比べると群をを抜いてうまい。本作はこの彼の特徴を最大限活かした作品となっている。
幽霊たちのあらすじ
探偵ブルーは奇妙な依頼を受けた。ブラックを見張るようにと。真向いの部屋から、ブルーはブラックを見張り続ける。だが、ブラックの日常に何の変化もない。彼は、ただ毎日何かを書き、読んでいるだけなのだ。ブルーは空想の世界に彷徨う。
登場人物は全て色の名前。探偵のブルー、探偵対象のブラック、探偵依頼者のホワイトの3人。舞台はブルー&ブラックが住んでいるアパート。基本的に探偵ブルーがブラックという男を監視し続けるだけの物語。
この小説の設定だけ聞くと退屈で飽きそうな物語に見えるが、私は全く退屈することなく一気に読了した。100ページと短いので是非皆さんに読んでもらいたい。さて本書の魅力を書いていく。
孤独とは何か
ブルーの心情の変化が面白い。ブルーはブラックが何者なのか、何のためにブラックを見張るのかと考え色々な妄想を膨らませる。妄想すればする程、自分を見失っていきそのまま物語が終わる。本書はブルーの妄想で物語が進んでいくのだ。
一年中ブラックを見張っているブルーは孤独と戦うことになる。しかし、ブラックもまた孤独と戦っていたのだ。ブラックは一年中書物を書いている。本を書く時、本を読む時には孤独を排除することができない。本を書くこと=見張ること、両者は一年の間お互いに孤独に苛まれることになる。
ブルーはブラックの監視を続けるうちにブラックに親近感を感じ、監視をしなくてもブラックの行動が分かるようになる。孤独を紛らわすためにブルーの中にブラックを取り込んだとも言える。
タイトルの「幽霊たち」にも孤独の意味が含まれている。文中の会話は下記。
「書くというのは孤独な作業だ。それは生活をおおいつくしてしまう。ある意味で、作家には自分の人生がないとも言える。そこにいるときでも、本当はそこにいないんだ。」「幽霊ですね。」「その通り。」
また、本作はエドガー・アラン・ポーの群衆の人という短編小説と共通点が多い。どちらの作品も、ある人がある人を見張りそのまま感情移入していくのだ。そして最後には見張っていた頃の孤独を忘れ、見張っていた人と見張られていた人の境界性がなくなり、同一化していく。同一化すると次第に自分がいま何処にいるのか分からなくなり、抽象的な世界に吸い込まれる。
100ページ程にも関わらず、自分に孤独とは何か?自分と他者との隔たりは何か?を色々と考えさせられる本である。孤独を考えさせられる本だから、私は一人旅の時によく本書を持ち歩く。自分自身を孤独な状態において読むと、ブルーの気持ちが痛いほど伝わってくる。旅がしたくなるお勧めの本として、本書を下記の記事でも紹介しているので参考にどうぞ。
海外旅行・バックパッカーがしたくなる旅小説10冊!

チャンネル登録、宜しくお願いしますー!
関連記事
-

-
【武器としての書く技術 – イケダハヤト】ブロガーに捧ぐ心構えと文章力の指南書
本書はブロガーの基礎となる心構え、記事を書く文章力の指南書である。騙されたと思って、全てのブ
-
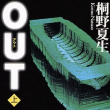
-
【OUT – 桐野夏生】深夜の弁当工場で働く主婦たちの犯罪
[amazonjs asin="4062734486" locale="JP" title=
-
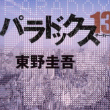
-
【パラドックス13 – 東野圭吾】13時13分13秒に突如人類が消えた…
ページを捲る手が止まらなかった。緊迫感の中で起きる思いがけない出来事の連続に圧倒された。貴志
-

-
【脳内麻薬 – 中野信子】快楽物質ドーパミンをコントロールしよう
快楽物質のドーパミン。これは50種類ある神経伝達物質の中で、快感を増幅するするための物質であ
-

-
【他人事 – 平山夢明】万人受けしない残虐と不条理に塗れた14編
人間の暗い部分、触れては行けない部分、人としてやってはいけない事が全て詰め込まれているこの作品。暴
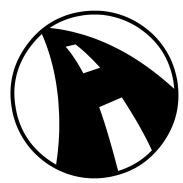 On The Road
On The Road